このメルマガの読者には、これからCMMIモデルを利用する人や、すでに利用中でベテランの域に達している人まで様々な方がいらっしゃるかと思いますが、誰しも最初はモデルの解釈に困ったり、どのように利用していけば良いか分からずに悩んだりしたのではないでしょうか。
CMMIに限らず、例えばISOやITIL、PMBOKのような世の中にあるプロセスモデルやフレームワーク、知識体系と呼ばれるものの利用を新たに開始する際は、少なからず解釈や利用方法に悩んだり、困った挙句に利用を諦めてしまったりすることもあると思います。
これらのモデルの類は、自らのスキルや自組織の改善に役立つ情報がまとめられていますので、うまく使えばとても良い効果を出せるはずですが、そのためには内容をしっかり理解して、自由自在に活用するスキルを身につけたいところです。
今回は、プロセスモデルの類を自由自在に使えるスキルをどうやって身につけるかを、私の長年の経験にもとづいてご紹介したいと思います。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
1.聞く
まずはモデルの全体像を手っ取り早く把握するために、専門家や有識者の話を聞く機会を得るのがよいです。
自分であれこれ悩んで右往左往するよりは、詳しい人に聞いてしまった方が、ゴールへの道筋が見えやすくなり、自分で調べ物をする際の糸口がつかみやすくなって、迷わずにすみます。
身近に詳しい人がいればその人に直接聞いたり、予算が確保できれば専門のセミナーを受講するなどするとよいでしょう。
CMMIであればCMMI入門コースなどがあります。
2.読む
そのプロセスモデルの書籍を入手し、一度全体を通して読みます。
一読しただけでは理解するのは難しいので、必要に応じて繰返し読みます。
できれば関連の解説書や参考書籍なども合わせて入手し、理解の補助とするとよいでしょう。
繰返し読むのに、書籍を持ち歩いて通勤中の電車の中などで読むのは良い方法だと思いますが、こういったモデルの書籍は分厚くて重いことが多いのが難点です。
対策として、PDFファイルや電子書籍でモデルを入手して、タブレット端末に入れて持ち歩くということを私はやっています。
スマホの画面は小さいので、7インチ以上のサイズのタブレットがおすすめです。
3.書く
読んだだけでは頭に残りにくいので、次は書いて覚えます。
書く行為として、手書きとワープロ打ちの二通りの方法があります。
それぞれ一長一短がありますので、両方を駆使すると良いでしょう。
記憶に定着させるには、脳が刺激されるので手書きが良いらしいです。
私はCMMIの勉強を始めた頃は、プロセス領域やプラクティスの関連図をノートに書き出すことをよくやっていました。
絵が視覚に訴えることができるので、覚えるにはより効果的です。
ワープロ打ちした資料は、劣化しない電子データとして保存ができ、検索性が高いので、復習がしやすいのが特徴かと思います。
プロセスモデルの類は独特の用語が定義されていることが多いので、キーとなる用語を書き出して自分用のまとめファイルを作ると便利です。
4.ひもづける
プロセスモデルは抽象的でわかりにくい、と言われることがあります。
モデルは、現実世界の具体的事例の中で良いとされる活動、いわゆるベストプラクティスを、どの事例でも当てはめられるように、【抽象化】という行為を通して一般的な言葉に落とし込んで作られています。
具体的事例 → 【抽象化】 → モデル
なので、モデルの言葉を自分のよく知っている具体的事例にひもづけて考えてみるという【具体化】をやってみると、理解度が上がることが期待できます。
具体的事例 ← 【具体化】 ← モデル
例えば、CMMIの各プラクティスに対して自分の関わっているプロジェクトや組織のドキュメントに当てはめてみると良いでしょう。
このように、モデルの要素と現実世界の活動のひもづけのほかに、
・モデルの中の関連する要素同士のひもづけ(例えば上記の「書く」のところで説明したプラクティス間の関係)や、
・対象のモデルの要素と他のモデルの類似要素のひもづけ(例えば用語の定義の違い)
など、様々な要素のひもづけを確認し、体系を整理していきます。
それらの活動によって、モデルとその周辺情報がひもづいた知識が蓄積され、自分の頭のなかに脳内マップのようなものが出来上がりますので、情報を引き出しやすくなります。
5.話す(または発表する)
最後に、ここまでの成果を誰かに話すことで、知識が使えるものになっていきます。
上司に報告したり、社内の説明会で伝達したり、奥さんに説明したり(モデルの話なんて聞いてもらえないかもしれませんが)、ブログやメルマガで発表したりするのもよいでしょう。
誰かに話すためには、きちんと話せるようにまとめないといけませんので、そこで知識が再整理されます。
場合によっては、上記の1~4を繰り返して、自由自在度をあげていきましょう。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
以上、私なりのプロセスモデルの学び方を紹介させて頂きました。
学び方はこれだけではないと思いますが、一例として参考になれば幸いです。
最近、とあるミッションで私もCMMI-DEV以外のモデルを学ぶ必要性に直面していまして、上記でご紹介させて頂いた方法で習得に励んでいます。
新しいモデルを学ぶのは大変な反面、新鮮な気持ちで取り組めるのでとても楽しいです。
身につけるまでは長い道のりなので、楽しんで取り組むことは重要ですね。
皆さんも「好きこそものの上手なれ」の気持ちで取り組んでみてください。
第142号:プロセスモデルの学び方
2016年01月25日
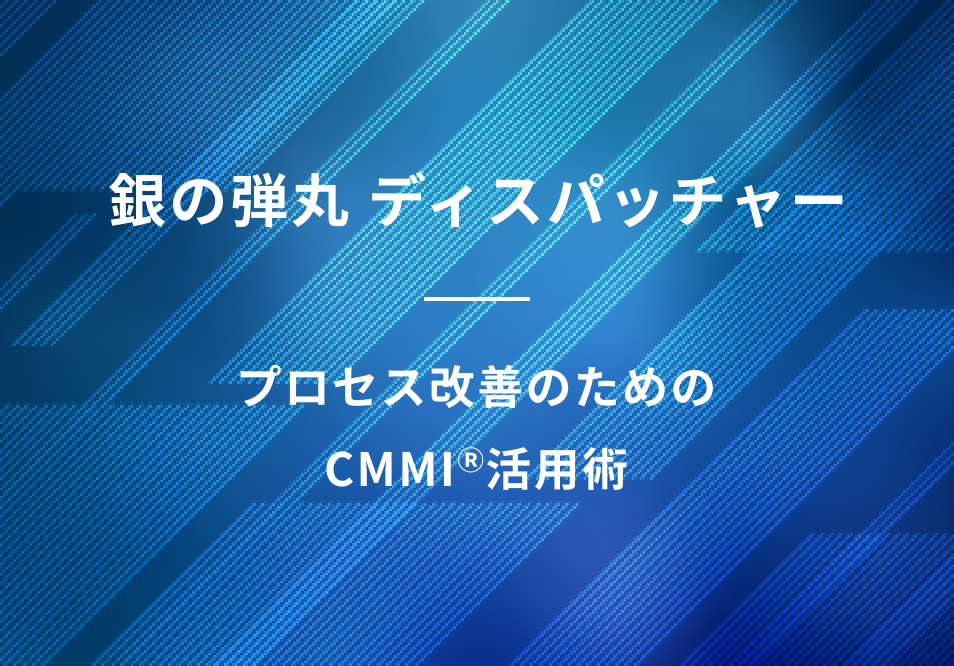
-
プロセスモデルの学び方

