数年後にはAI(人工知能)に奪われる仕事がたくさん出てくるという話を最近よく聞きますので、強力な商売相手となるかもしれないAIのことを知るために、年末にスマートスピーカーを買いました。
とりあえず、いろいろ試してみました。
「アレクサ、CMMIについて教えて」とか「プロセス改善って何?」とか聞いたら、
「すみません、よく分かりません」
「今はわかりませんが、もっと勉強しておきます」
などと回答されました。
次に「アレクサ、品質管理について教えて」と聞いたら、
「こんな説明が見つかりました。品質管理は顧客に提供する商品およびサービスの品質を向上するための、企業の一連の活動体系」
と答えました。おっ、これはだいぶマシです。しかし、どうやらこれはウィキペディアの冒頭部分を読んだだけのようです。
最後に、あまり期待せずにちょっと難しめの質問として、
「アレクサ、ソフトウェアのバグを減らすためにはどうしたら良いと思う?」
と聞いたら、
「すみません、わかりません」と、また謝られました。
現時点では、CMMIやプロセス改善を教える仕事はAIよりも人間に分があるようですので、当面はSEPGやコンサルタントの方々の仕事は奪われなくてすみそうです。
もう少し進化したら、セミナーのサブ講師として雇用して、用語とかを解説してもらうのもいいかなあと、夢を膨らませています。
第166号:AIに教えてもらうCMMI, 気づきを得るためのフレームワーク活用
2018年01月25日
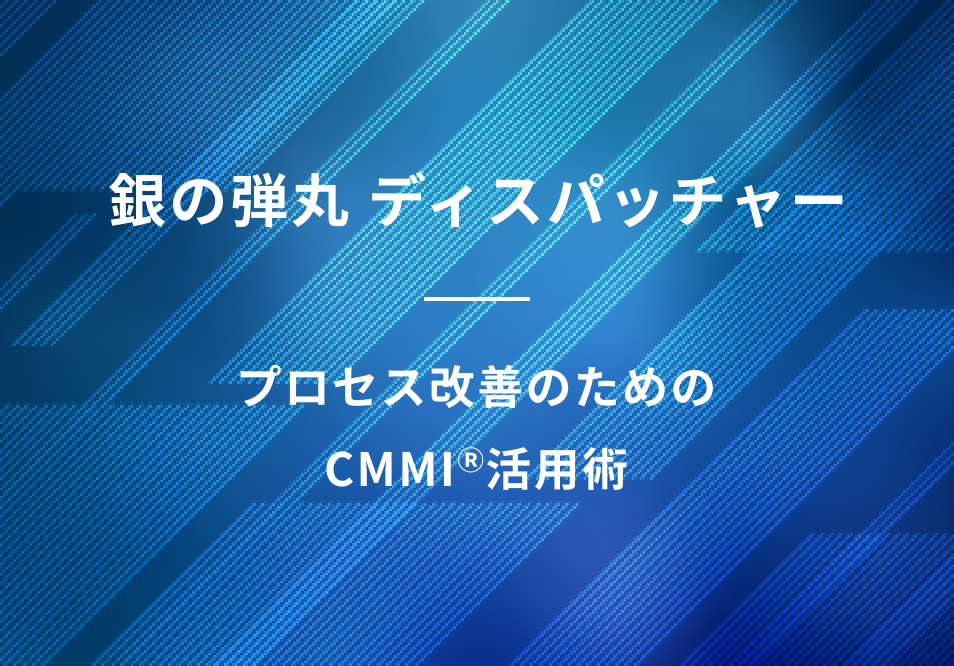
-
AIに教えてもらうCMMI
気づきを得るためのフレームワーク活用
プロセス改善活動を成功させるには、活動をうまく実施できるかどうかの前に、まず課題となる改善の芽に気づくことができるかどうかが重要かと思います。
気づくことができる人になるにはどうしたら良いでしょうか。
以前読んだ書籍の中で「バグはなぜ作られるのか?」というコラムがあり、以下のような解説がありました。
・バグはプログラムのコードに潜んでいる。プログラムを作るプロセスから考えると、仕様書をインプットに、人がコードに落とし、プログラムをアウトプットしているので、バグは人が作り出していると言える。
・問題は人にあるらしいので、バグを出さないようにするために、人を叱ったり、教育したりといった対策が行われる。
・しかし、それだと根本解決にならずに再発する可能性が残る。そこでもう少し考え方を広げて、問題を「バグは人が作った」から「なぜ人はバグを作らざるを得なかったか」というふうに置き換えて考えてみる。
・すると原因は、プログラムを作成した時のまわりの「環境」にあるのでは、ということが分かる。時間がなくてしっかりテスト出来なかったとか、仕様書がわかりずらかったとか、などに気づく。
・デキる人に共通していることとして、まわりに何があるのかというに気づける「視点」を持っている。
このコラムを読んだときに感じたのが、仕事がデキる人が持っているであろう、まわりに何があるのかに気づける「視点」を得るのに、CMMIのようなベストプラクティスを体系的にまとめたフレームワークが役立つのではないか、ということ
でした。
例えば、作成したドキュメントをレビューしたときは、CMMIの関連プロセス領域のゴールやプラクティスを思い浮かべ、足りない要素に気づいて改善点をあげたり、自部門のプロジェクト管理やエンジニアリングのあるべき姿を整理する時には、CMMIモデルを参考にプロセスの全体像を描いたりできます。
CMMIモデルが体に染み込んでいると、こういったことが非常に高速にできるようになります。実際、私自身がそうでした。CMMIを学ぶ前よりも今の方が、何に対しても多くの気づきが得られるようになりました。
一流の人の気づきを得るために、何か1つフレームワークを極めてみるのが大事ではないでしょうか。世の中で役立つフレームワークはCMMI以外にもいろいろありますので、自分の肌に合うものを身につけるといいでしょう。
もうすぐ、CMMIの次バージョンであるV2.0がリリースされます。CMMIを今まで学んでいた人も、これから新たに学ぼうと思っている人も、新しい視点を得られる良いチャンスですので、取り組んでみてはいかがでしょうか。

