プロセス改善ストーリーをお届けします。CMMIを使ったプロセス改善活動で悩むポイントや事例などを、初心者向け解説本でよく見かける会話形式の文章で解説していきます。
これは一時期ほぼ連載のように書いていてわりと好評だったシリーズなのですが、最後に書いた回を調べたらなんと7年も前だったので初めて読むという人も多いかもしれません。かなり久しぶりなので物語の背景も少し書いておきます。
<ストーリーの背景>
舞台は中堅ソフトウェアベンダの株式会社フジコソフト。新たに改善グループに配属されSEPGとして活動していくことになった野比は、同グループの骨川、源、そしてリードアプレイザの資格を持つ外部のコンサルタントである土良とともにCMMIをベースにしたプロセス改善活動を進めている。
<登場人物> ()は会話文中の省略形
野比(野):改善グループのメンバ。新米SEPG。周りに頼りがち。
土良(土):CMMIコンサルタント。改善グループの相談に乗っている。参考書籍などを秘密道具のようにポケットから取り出すのが特技。
今回は、改善グループと開発現場との間にある壁について話し合っているようです。
第222号:プロセス改善ストーリー:ある新米SEPGの1日(改善グループと現場の壁)
2022年09月22日
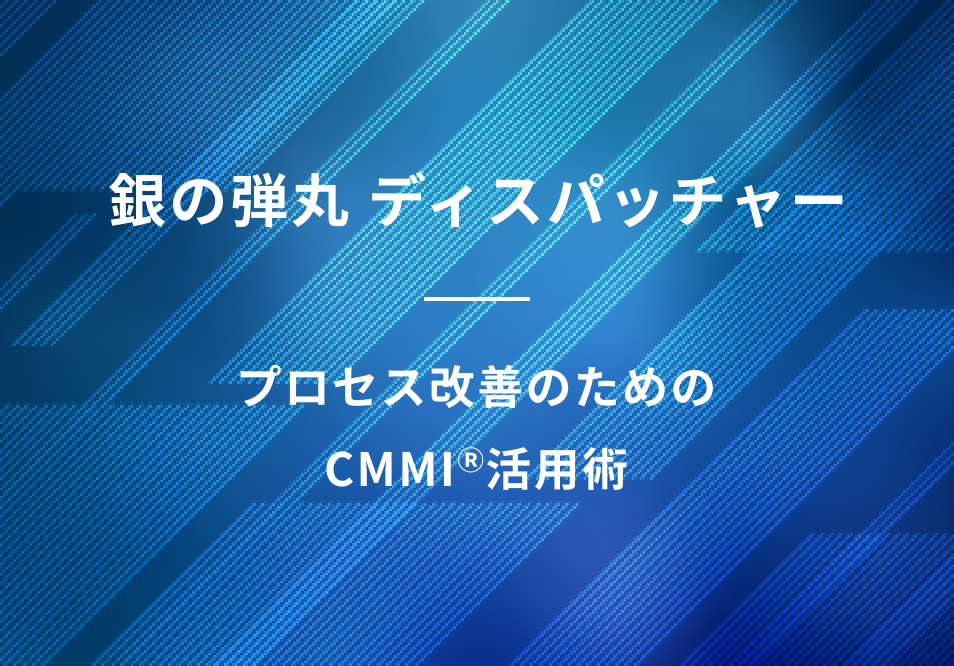
-
プロセス改善ストーリー:ある新米SEPGの1日(改善グループと現場の壁)
改善グループと開発現場との間の壁
野「土良さ~ん、ちょっと困ったことがありました。助けてください」
土「野比さん、今日はどうしました?」
野「先日、開発現場のリーダーの郷田先輩と、新しく導入しようとしている標準プロセスについて話し合っている時に『ぶっちゃけ、改善グループとオレら開発現場との間には壁があるよな』と言われました。
壁があるなんて自分では思ってなかったのでうまく受け答えできませんでした。どう答えたらよかったですかね?」
土「なるほど、開発現場の方が組織間の壁を感じるとおっしゃっているのですね。そうですね、組織の改善活動を推進するグループと、推進・導入される側の部署やグループが分かれている場合、組織間に見えない壁があると昔からよく言われています。
具体的に何が壁と感じるとおっしゃっていましたか?」
野「たしか、
・改善グループは標準プロセスを使え使えというが、必要性がわからないものがある。なくてもプロジェクトは進められるし、困らない。
・なぜ作るか分からない文書は作成コストをかけたくないが、忙しくて反論の時間も惜しいので、面倒だが作ってしまったほうが早い。なのでやらされ感がある。
・CMMIも何がすごいかいまいちわからない。といったことを言ってたと思います。いろいろまずそうなのはわかりますが、どうしたらいいでしょうか?」
土「一般に組織はある一定規模以上の大きさになると専門の部署が増え、仕事が縦割りになりがちになります。自分たちの役割を果たすことが最優先になると、部署間の壁が生じて連携がうまくできなくなります。壁ができると、各部署では業務が最適化されても、全社的には生産性低下や管理コスト増を招くことになりますので、よくない状況になります。
壁は会社全体での目的や方針、役割が理解されてない場合にも生じやすくなります。
改善グループは改善活動の推進、開発現場はお客様向けシステム開発を成功させ利益を上げることがそれぞれミッションになるかと思いますが、改善グループの活動が開発現場のミッション達成に貢献するということの理解は、開発現場の人たちから得られていますでしょうか。
また、郷田さんが感じている壁は、標準プロセスやCMMI導入の目的や方針の理解が十分得られてないことからきているのではないでしょうか?」組織間の壁に対処するには
野「うーん、そうかもしれません。でも標準プロセスの使い方やCMMI導入の目的の説明会は現場向けに1回は実施しているんですけどねえ。イントラに説明資料もアップして、いつでも見れるようにはしてますし」
土「1回きりの説明で十分に伝わるとは限りませんよ。
CMMI V2.0モデルの第2部を読んでみましょう。CMMIを首尾よく導入するには意思疎通が重要であると以下のようなことが説明されています。
・典型的に意思疎通の欠如は一番の問題である
・頻繁な意思疎通は、変更によって人員が経験する不安感を低減する
・90%の人員が理解して行動するようになるには、メッセージを複数の方法で複数回伝達しなければならない、という研究結果もある
また、類似の話で『6度6割』という言葉をご存知でしょうか」
と言って土良はポケットから1冊の書籍を取り出した。
土「『6度6割』は『抵抗勢力との向き合い方(日経BP社)』という書籍で紹介されていますが、6回伝えてようやく6割伝わるという意味だそうです。
そんな回数出来ないと思ったかもしれませんが、相手にしっかり理解してもらうためには、そのくらい工夫と伝える努力が必要という意識を持つ必要があるということでしょうね」
野「うう、たしかに十分伝えきれてなかったかもしれません。
そういえば郷田さんは、イントラの説明資料も見る時間もないし、確認もできていないとも言っていました。あらためて当活動の目的や標準プロセスの意義などの説明を丁寧に行ったほうが良さそうです。
しかし、面と向かって壁があるなんてショックなこと言わないでほしかったなあ。野比のくせに生意気だぞとか言われるし」
土「でもちゃんと伝えてくれるというのは逆にありがたいことですよ。表面化していないだけで、こういった不満や指摘を心に留めている人はもっといると思われます。
前述した書籍では、変革への抵抗勢力には以下のような4段階のレベルがあると紹介されています。
・レベル1 モヤモヤ/違和感
・レベル2 まっとうな指摘
・レベル3 何が何でも反対
・レベル4 潰しにかかる
レベルが上がるほど強い抵抗ということですが、郷田さんはレベル1~2といったところではないでしょうか。
しっかり、活動の共感と共有を行いながら十分な意思疎通を行って理解を得られていけば、感じていた壁は徐々に取り除けるのではないでしょうか」
野「そういう考え方があるんですね。レベル1のモヤモヤを抱えている人はまだいそうですし、レベル3以降の人が今後顕在化してこないようにしっかり対処していく必要がありそうですね」
土「あと組織間の壁に対処してプロセスを馴染ませていくためには、CMMI V2.0では習慣と持続性の維持のプラクティス領域である統治(GOV)、実装のインフラ(II)の考え方も有効でしょうね。
上級管理層が目標や方針を打ち出して改善活動をしっかり支援していくこと、浸透させていくための資源やトレーニングを確保することなどのプラクティスを実施していくことで、プロセスが習慣化されていきます。
ほとんどの人は、寝る前の歯磨きは意識しなくても当たり前にしていると思います。最初は抵抗感があったり意識してやらないと忘れがちになったりするプロセスも、習慣化すれば歯磨きのように当たり前に実施できるようになります。
組織のプロセスがそんな状態になれば、組織間の壁というのも感じにくくなるのではないでしょうか」
野「うーん、そんな状態を目指したいですね」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
<野比のノビノビ日記 ~今日のまとめ~>
組織間の壁を感じさせないようにするのはなかなか大変だなあ。意思疎通が大事なのはわかったけど、他人に誤解なく伝えるのは難しいよ。言いたいことを正確に翻訳してくれるコンニャクとかあったらいいのに。郷田さんから「心の友よ」と言ってもらえるようにがんばってみよう。
さて、今日の話をまとめておこう。
・組織間の壁は仕事の縦割りの影響や、目的・方針・役割の理解不足などから生じる。自部門の役割を果たすことが最優先になり、部署間連携や全社最適の観点で動けなくなる状態。管理コスト増などよくないことが起こりやすくなる。
・標準プロセスやCMMI導入の目的・方針の理解が不十分なら壁が生じる。説明は一度だけでは十分でないかもしれない。6度6割というくらい意思疎通が重要。
・GOVとIIでプロセスを習慣化させる。

