おそらく組織の改善活動の中心を担っているであろう読者の皆様の多くは、日頃から組織のプロセスをより良くすべく頭を悩ませ、日夜組織の内部外部問わず情報収集にいそしんでおられることでしょう。
今回は、そんな皆様の知的好奇心を刺激して止まない(かもしれない)データが公開されているサイトをご紹介します。
皆様の改善活動の参考になれば幸いです。
第53号:CMMIのランキング その2
2008年08月25日
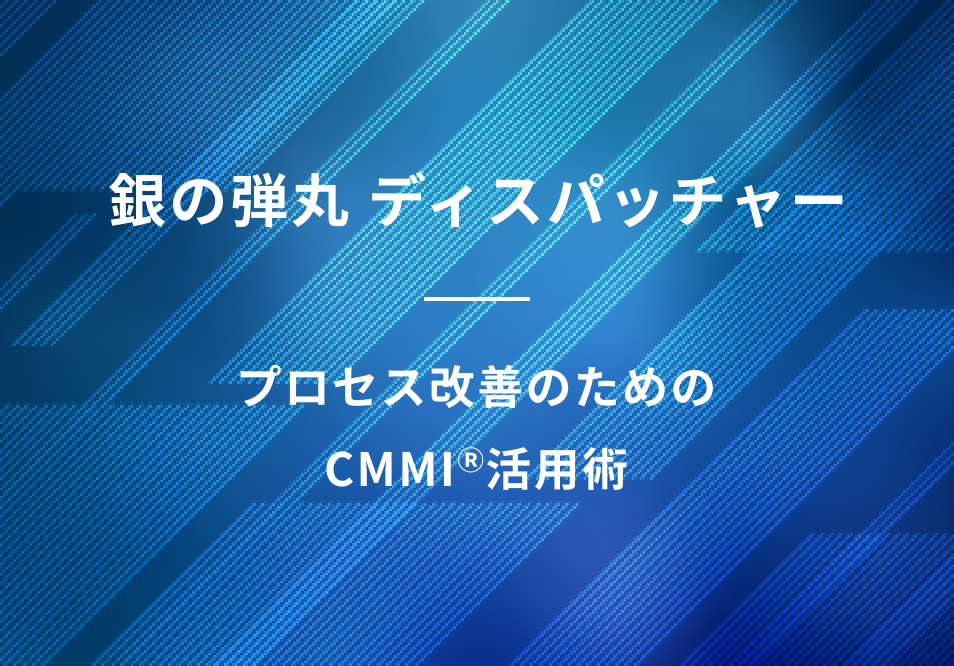
-
CMMIのランキング その2
1.Process Maturity Profile
CMMIはソフトウェア開発能力を測る世界的基準と言われているけど、実際どのくらい広まっているのかとか、どのくらいの規模の組織がCMMIに取り組んでいるのかとか、アプレイザルで落としやすいプロセス領域は何なのかなど、調べたいと思ったことはありませんか?
そんな時はコレ、SEIのMaturity Profileです。
http://www.sei.cmu.edu/appraisal-program/profile/profile.html
Maturity Profileは、SEIがリードアプレイザから送られてきた正式アプレイザル(SCMAPI)の結果がまとめられて公開されたものです。
毎年2回、3月と9月頃のリリースされます。
実は昨年も丁度同じ時期にこのレポートの事を紹介させて頂いたのですが、今回は1年前とデータがどう変わったかも含めてご紹介しましょう。
※現在の最新版は2008年3月時点のものです。()内の数値は2007年3月時点のものです。
○現在の状況
2002年4月から2008年1月までにSEIに報告されたアプレイザル数、組織数、参加企業数、再びアプレイザルを実施した組織数、プロジェクト数、アメリカ合衆国以外の組織の割合が紹介されています。
アプレイザル数 3,113(←1,964)
組織数 2,674(←1,712)
参加企業数 1,882(←1,084)
再アプレイザル組織数 361(← 208)
プロジェクト数 14,620(←6,713)
USA以外の組織 68.6%(←65.5%)
年間1,000件以上のアプレイザルが実施されてるんですね。
また、アメリカ合衆国以外の国でのアプレイザル実施割合が増えてます。
どの国が多いのかというと、それは以下参照。
○アプレイザルを実施した組織を含む国の数
61カ国(←50カ国)
○国毎のアプレイザル数
1位 アメリカ 1,034(←718) 31%
2位 中国 465(←240) 48%
3位 インド 323(←202) 37%
4位 日本 220(←172) 22%
5位 フランス 112(← 72) 36%
6位 韓国 107(← 78) 27% ※%は伸び率
アジア圏が結構上位に来ています。注目は伸び率トップの中国でしょうか。
伸び率で言うと、スペイン、アルゼンチン、ブラジル、マレーシアでも結構増えてきているようです。
CMMIが世界に広まっていっているのを感じます。
○組織のサイズ(従業員の人数)
100人以下 50.8%(←45.9%)
101~200人 19.8%(←19.6%)
201人以上 29.4%(←34.5%)
100人以下の組織が50%を超えました。CMMIが世界に広まるにつれ、小規模の組織でもアプレイザルを実施するケースが増えてきたという事でしょうか。
○プロセス領域(PA)のプロファイル
成熟度レベルが1や2という結果だったアプレイザルのうち、PAが評価されたもの(Rated)と満足していると判断されたもの(Satisfied)の割合が示されています。
RatedとSatisfiedの差が大きいPAほど、ゴールに影響を与える弱みが検出されやすい傾向にある要注意PAと言えそうです。
成熟度レベル2と3について、上位5つずつあげてみます。
成熟度レベル2 成熟度レベル3
------------------------------------- ---------------------------
1位 構成管理(CM) 統合プロジェクト管理(IPM)
2位 プロジェクト計画策定(PP) 検証(VER)
3位 プロセスと成果物の品質保証(PPQA) 技術解(TS)
4位 測定と分析(MA) 決定分析と解決(DAR)
5位 要件管理(REQM) 要件開発(RD)2.ATLAS
もう1つご紹介したいのが、リードアプレイザのPat O'Tooleさんの調査レポートで、ATLASというものがあります。
Pat O'Toole氏のHP
http://www.pactcmmi.com/index.html
ATLASは、"Ask The Lead AppraiserS" の略称で、数ヶ月に1回、世界中のリードアプレイザやプロセス改善担当者向けにEメール上でアンケートを実施して、その結果をPatさんが集計して公開しているものです。
その対象となるトピックは、モデルの実装上の課題、評定やトレーニングに関する課題など多岐に渡り、実に興味深い内容になっております。
その中の1つ、「CMMIモデルのプラクティスの中で、最も解釈上の問題に遭遇すると考えられるかのはどれか」という調査結果がありますのでご紹介しましょう。
(ATLAS 7: Interpretation Issues)
成熟度レベル2と3のプロセス領域内の固有プラクティス、共通プラクティスについて、上位5つずつあげてみます。
皆さんも思い当たるフシがあるのではないでしょうか?
※CMMIのバージョンは1.1です。
成熟度レベル2のプロセス領域の固有プラクティス
--------------------------------------------------------------------
1位 REQM SP1.4 要件の双方向の追跡可能性を追跡する
2位 PP SP2.3 データ管理について計画する
3位 MA SP1.1 測定目標を確立する
4位 PP SP1.2 作業成果物とタスクの属性の見積りを確立する
4位 CM SP3.2 構成監査を実施する
成熟度レベル3のプロセス領域の固有プラクティス
--------------------------------------------------------------------
1位 RD SP3.1 運用の考え方と運用シナリオを確立する
1位 DAR SP1.1 決定分析のための指針を確立する
3位 TS SP1.2 運用の考え方と運用シナリオを発展させる
3位 TS SP2.2 技術データパッケージを確立する
5位 RD SP3.5 要件の妥当性を確認する
共通プラクティス
--------------------------------------------------------------------
1位 GP2.8 プロセスを監視し制御する
2位 GP2.2 プロセスを計画する
3位 GP3.2 改善情報を集める
4位 GP2.9 忠実さを客観的に評価する
5位 GP2.7 直接の利害関係者を特定し関与させる月刊ブックレビュー
【書名】ソフトウェア品質知識体系ガイド ―SQuBOK Guide―
http://tinyurl.com/6k84zu
【編者】SQuBOK策定部会
【出版社】オーム社
【発行】2007年11月29日
【ISBN】978-4-274-50162-3
【本の内容】
序章 SQuBOKガイド戦略
第1章 ソフトウェア品質の基本
第2章 ソフトウェア品質マネジメント
第3章 ソフトウェア品質技術
【レビュー】
品質に関することがいろいろ載っています。でも本書はソフトウェア品質に関する知識体系そのものではありません。それは別の場所にあります。本書はそれにアクセスするためのガイドです。
ソフトウェア品質に関することで何か知らないものに出会ったときに、本書を辞書のように使うとよいでしょう。たいていのことは載っていると思います。でもあまり詳しくは載ってないので、もっと詳細に知りたかったら、そのときは参考文献や関連文献を読みましょう。

