プロセス改善活動をうまく進めるには、改善目標を明確にするのが重要なポイントのひとつです。
よい目標設定をするにあたっては、SMARTというフレームワークがよく使われています。
S(Specific) 具体的である、曖昧でなく明確である
M(Measurable) 測定できる、達成判断できる
A(Attainable) 達成できる、現実的である
R(Relevant) 上位の目標と関連がある
T(Time-bounded) 期限が設定されている
SMARTは目標設定において非常に有用で、当メルマガでも何度かご紹介しておりますし、皆さんの組織でも活用されているのではないでしょうか。
ただ、一方でSMARTには以下のような課題や限界が指摘されているようです。
・内発的動機を引き出しにくい
- 数値や期限が目的化しやすく、やらされ感を生み出しやすい
- とりあえず間に合わせるという行動になることがある
・失敗や試行錯誤が許容されにくい
- 達成可否が評価指標となり、実験や学習の余地がなく、
チャレンジの風土が醸成しにくい
・変化に適応しにくい
- 一度決めた目標に固執し、環境変化に合わせた柔軟な軌道修正がしにくい
・個人やチームの創造性や関与度が下がる
- 「自分ごと化」しにくく、自分たちで目標を育てる余地が少ない
もちろん、SMARTをきちんと使えればこういった課題も払拭できるはずですが、うまくいっていない組織やSMARTについてモヤモヤを感じている方は、目標設定のあり方について何か新しい知恵がほしいところでしょう。
最近読んだ「冒険する組織のつくりかた -軍事的世界観を抜け出す5つの思考法- (著:安斎勇樹氏、テオリア社発行)」という書籍で、「ALIVE」という目標設定の新しいフレームワークが提案されており、これらの課題に効果がありそうだなと思いましたのでご紹介します。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
ALIVEとは
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
本書は、これまでのビジネスで蔓延していた「軍事的世界観」を、これからの不確実な世界の中で、各人が新しい価値を探求していく「冒険的世界観」へアップデートさせていくための考え方が体系立ててまとめられた組織論の本です。
冒険する組織となるための5つのレンズ(目標、チーム、会議、成長、組織)についての基本原則や実践方法が紹介されているほか、CCM(Creative Cultivation Model)という組織モデルなどが紹介されており、個人的にも非常に興味深く読めました。CCMとCMMって何か語感が似ていてシンパシーを感じますし、機会があればこちらも触れていきたいところですが、本日はALIVEについてご紹介します。
ALIVEの観点は以下のようなものです。
A(Adaptive) 変化に適応できる
L(Learningful) 学びの機会になる
I(Interesting) 好奇心をそそる
V(Visionary) 未来を見据える
E(Experimental) 実験的である
●A(Adaptive) 環境変化に適応しやすい、柔軟な目標を立てる
一度設定した目標は、変更せずに最後までやり抜くことが正しいと思いがちです。
もちろん、目標達成に向けて粘り強く取り組む姿勢は重要ですが、変化が激しい現代においては、同じ目標にこだわりすぎたり目標が具体的すぎたりすると融通がきかなくなるリスクがあります。
まずは仮説としての暫定目標を設定し、環境変化に応じて柔軟に目標を調整しながら進めます。
●L(Learningful) 目標を追いかける過程を、学びの機会に変える
達成したい成果のみにフォーカスせずに、達成に向けてのアクションがどのような学びの機会になるかを踏まえて目標を表現します。
例:生産性を前年比10%アップさせる
→設計・開発の学習を進めながら知識習得し生産性を前年比10%アップさせる
●I(Interesting) 目標そのものを興味深く、好奇心をそそるものにする
個々のメンバの内発的動機につなげるため、目標は好奇心をそそるような表現にします。
例:管理ツール見直しにより管理作業工数を平均5%削減する
→チームで管理作業の無駄ポイントを探す工夫選手権を開催し、管理作業工数を5%削減する
●V(Visionary) 予測不可能な未来に対して、つねに前向きな意思を込める
責任感や義務感、予測から目標を立てるのではなく、「こうしたい」「こうなりたい」という自分たちの前向きな気持ちやビジョンを目標の表現にこめます。
●E(Experimental) 不確実な環境でリスクを冒して、実験的要素を含める
不確実な環境下においては、単に前例踏襲の目標にするのではなく、わからなさに向き合い、ある程度リスクをとりながら実験的要素を目標に組み込んで、よりワクワクする目標にしていきます。
SMARTとALIVEの違いをもう少しざっくり説明すると、SMARTな目標が「明確で組織が管理しやすい目標」だとすると、ALIVEな目標とは「メンバがワクワク感を感じる目指したい目標」といったところでしょうか。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
ALIVEな目標の例
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
以上を踏まえて、ALIVEな目標設定を試してみましょう。
「ソフト開発におけるシステムテストでの不具合密度を年度末までに部門全体で○%改善する」という、ソフト開発組織においてわりと一般的な目標をALIVEの観点で書き換えてみます。
↓
「ユーザーに"安心して使える"と言ってもらえる品質を目指して、チームで学び合い、試行錯誤しながら、不具合の予防方法を探求し続ける1年にする」
変化への適応(A)や実験的な要素(E)を含め、取り組みの過程で学びの機会を得て(L)、好奇心をそそる活動を含むようにし(I)、安心できる未来を見据えた目標(V)の表現になるよう意識した結果、こうなりました。
SMARTな要素は減りましたが、ワクワクする前向きな気持ちは出せたように思います。
では、ALIVEな目標に取り組んだら、SMARTな目標は不要になるかというと、そんなことはありません。
書籍でも、すでにSMARTな目標が設定されているなら、それをよりALIVEなかたちにアレンジしていくアプローチが現実的と紹介されていました。
私が関与している組織でも目標設定はSMARTになるよう心がけておりますが、今後はALIVEな観点も意識して、より達成に向けて活動したくなるワクワクする目標を作れるようにしていきたいと思います。
第254号:SMARTな目標に窮屈さを感じたら:ALIVEな目標設定とは
2025年05月23日
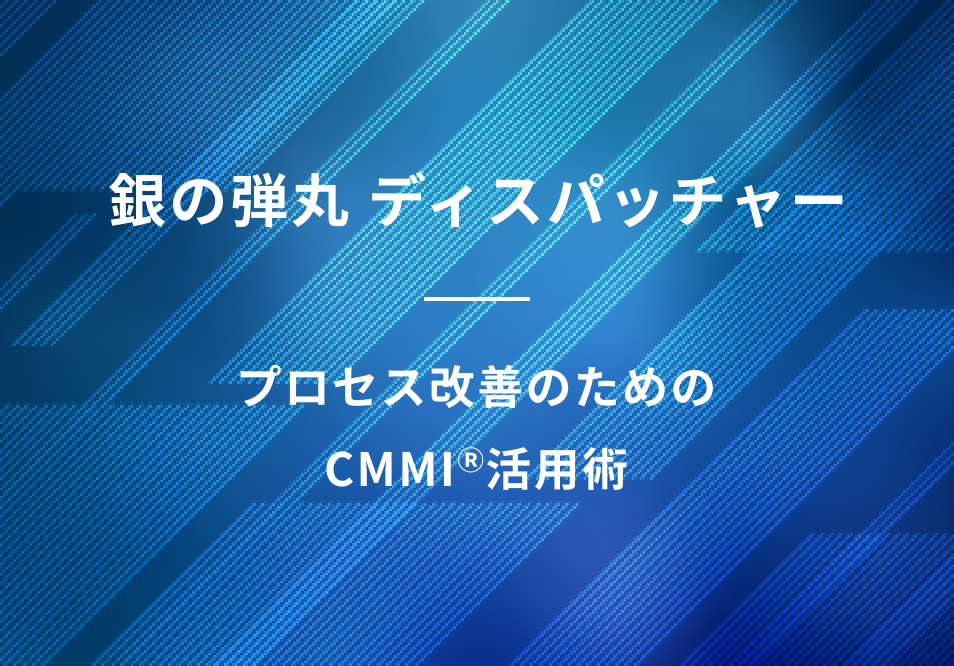
-
SMARTな目標に窮屈さを感じたら:ALIVEな目標設定とは
-
『5分でできる! ソフトウエア開発プロジェクトCMMI V2.0 セルフチェック』
CMMIに照らして、自社のソフトウェア開発プロジェクトの状況が簡単にチェックできます。
https://www.daiwa-computer.co.jp/cmmiselfchk2/大和コンピューターは、CMMI Instituteとのパートナ契約の下、公式のCMMIコースや、CMMIの成熟度レベルを判定するアプレイザル等のサービスをご提供しております。
▼サービス事例
・組織のメンバにCMMIの概要を伝える、トレーニングコース
・現在のプロセスの改善の機会を明らかにする、ギャップ分析
・改善の機会に対する改善策の検討の参加
・標準プロセスや各種テンプレートの作成活動に対する支援
・御社にインストラクタを派遣して実施するCMMI Institute公式CMMI入門コース
皆様のニーズに柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽に下記までご連絡下さい。
https://www.daiwa-computer.co.jp/services/consulting/inquiries/

